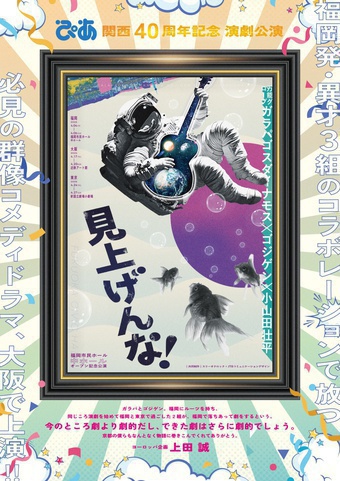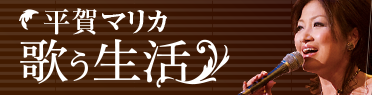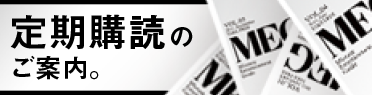2019年08月21日 <公演直前インタビュー!>きたやまおさむが語る音楽の効き目⁉︎
フォーククルセダーズの中心人物として「帰ってきた酔っ払い」「あの素晴らしい愛をもう一度」などの名曲を生み出したのち、医者を志し留学。その後、医師と音楽の活動を並行し、マルチに活躍するきたやまおさむ。今回のコンサートでは、専門である精神科の知識も活用し、かけがえのない音楽の魅力を紐解きます。
―九州大学を勇退されたのが2010年。現在もクリニックと音楽活動を両立されていらっしゃいますね。
1週間に4日間医者をやっているんですけど、週末は学会や協会の行事があることが多くて。そうすると毎年8月が私にとって「夏祭り」と称して音楽活動を行う期間になるんです。
自ら「祭り」というくらいだから、とても楽しみにしている時間です。今年は8月に3回コンサートがあります。
―そのうちの1回がこの名古屋でのコンサートですね。加藤登紀子さんとのトーク&コンサートとあります。
私は主にトークを担当するのですが、今回は皆さんに、人にとって音楽とはどんなものなのか?といったことをお話ししようと思っています。音楽は人生にとって欠かすことのできないものである。それをどういうふうに語るか?音楽は言葉だけではなくって歌っているわけなんです。まあ、私の持論があるので、なぜ音楽が必要なのか、心の健康にとって大事なのかという話をします。
―音楽は会話ではなくてメロディもあり、歌う人の声色もあります。
言葉以前の言葉みたいなものがあると思うんですよね。母親が子どもに聞かせる子守唄というのは子どもにとってその言葉の通りではなくて、それ以前の言葉みたいなものを含んでいるだろうと思うんですよね。「眠れ、よい子よ」と言葉で言っても眠らない子どもがほとんど。どう聴こえているかは、言葉以前の体験があろうかと。結局のところ私は、最初は歌なんじゃないかと思うんです、言葉は。お母さん皆んな、は子どもに向かって歌っているんじゃないかと思うんだよね。それを「マザリーズ」と呼んでいるんですけど、マザリーズというのは世界中のお母さんが子どもに話しかけるときに歌みたいに話しかけることを言うんです。母親言葉という意味ですね。この母親言葉というのは子どもとの絆を作るためには随分役に立っていて、声はピッチが高くてメロディを持っているんです。これを使ってみんな話している。それが子どもに使って、「〇〇ちゃん〜」って言っているわけですよね。
ー音楽の本質がマザリーズにあるということですね。
コンサートって、この声をみんな聴きに来るんじゃないかと思うんです。小さな子どもはマザリーズのメッセージを読み取ったりしているんだけど、そのうち成長し、マザリーズの内容を意識したり考えたりして、やがて言葉になっていくんだと思うんですけど。そういう言葉以前の言葉の要素をを歌自体が持っているので、私たちは歌を絶対に日常生活で必要としているんだと思うんですね。赤ちゃんはその言葉以前の言葉を聴いて安心して眠るのですが。この安心感を大人の私たちも必要とするわけです。では、どんな言葉や歌を聴くことで得られるのか。どんな聴き方でそれと出会うことができるのかという話をして、そんな話とともに聴く加藤登紀子の歌!これは入場料の三倍は役に立つよ(笑)。
―加藤登紀子さんの歌声も非常に重要になってきますね。加藤さんの歌の特徴は何かお感じになりますか?
それはやっぱり女性性が一つ中心にありますね。あの人は歌の中に虚しさがないのよね。虚しさを埋めてくれる一つの装置みたいなものを持っていますね。男性の歌には虚しい歌が多いと思うんですよね。女性の歌には寂しさみたいなものがあるけど、虚しさを歌わないね。一つの空間みたいなものが充実している。男性はそこにすごく隙間風が吹くんだろうな。そしてその隙間風を味わうんだけど、加藤さんと話してると「男はいつもそうよね」とかって言うよ。そしてエピキュリアン(快楽主義者)でもある。僕もそれは似ているところがあって、楽しむということはとても大事だと思っているし、どうしたら楽しいのかということをいつも心がけている。

―それは仕事も楽しむというような意味でしょうか?
これは僕の考えなんだけど、今、僕らは仕事をしているわけだよ。だから、ちっとも遊んでいない。私たちは。この遊びたい部分と大人として仕事をしなきゃいけない部分というのは分裂しているわけだ。あるいは、社会的に適応するためには大人をやっているけど、実は子どもみたいな部分があるわけじゃないですか。だから大人の人生と、子どもの遊びの部分が両方同じところにあるということは、奇跡みたいなものだと思うんだよね。そういうことは普通許されない。仕事は仕事。遊びは遊びであって、ここで遊んじゃいけないんですよ。だから、それを一緒のところに置くということはいいかげんだし、許されなくなりつつある。
それを、このトーク&コンサートで僕は両立させようと思っている。ここでは、考えることと歌うことの両立になるんだけど。
―きたやまさんご自身も日常生活と音楽活動を両立されていますね。
アマチュアバンドだった時には、充実した人生のほうが大事で、音楽というのはそのための方法だったと思う。女の子にもてたいからバンドを始める。女の子を口説くために歌を作るとか。それは歌のための人生じゃなくて、人生のための歌だと思う。ところが、職業的音楽家になった途端にこれが逆転するわけ。人生のための歌だったのが歌のための人生になっていく。それは僕からすればフォークソングじゃない。フォークソングは人生のための歌だったと思うんだよね。加藤登紀子さんもそういう人生だと思いますよ。だから、人は歌を通して加藤登紀子という人の人生を感じる。シャンソンというのはそういうものだと思う。
―きたやまさんにとってライブとはどのような場であるのでしょうか?
それはまさに、「祭りの1回性」というやつでしょうね。僕の著書では「聖なる1回性」という言葉を使っています。僕は、人生は1回だと思っている。コンサートも1回だと思うんです。ですから、加藤登紀子と北山修のこのコンサートも、多分ご覧になる方にとってこの日しかないものをご覧になると思うんですよ。人生が面白いことを一番具体的に示してくれるポイントですよね。この場におけるあなたとの会話も、これっきりですからね。この空気や面白さは当事者にしか分からないでしょう?これが一旦写真に撮られて、活字になった途端にその薄っぺらなこと!(笑)
8/22 THURSDAY 【チケット発売中】
加藤登紀子&きたやまおさむ
トーク&コンサート
◼️会場/愛知県芸術劇場 コンサートホール
◼️開演/15:00
◼️料金(税込)/S¥7,500 A¥6,500
◼️お問合せ/中京テレビ事業 TEL.052-588-4477(平日10:00〜17:00)
※未就学児入場不可 ◎共催/@FM
2019年08月11日 <観劇レポート!>村上春樹原作の舞台「神の子どもたちはみな踊る after the quake」
『神の子どもたちはみな踊る』は、1995年の阪神・淡路大震災の後に出版された村上春樹の連作同名短編集より、「かえるくん、東京を救う」と「蜂蜜パイ」の二作品を基にして構成された舞台作品。戯曲を担当したフランク・ギャラティはアメリカ出身の演出家・俳優・脚色家で、同じ村上の『海辺のカフカ』の脚色も担当している。『海辺のカフカ』は故蜷川幸雄により演出され、今年上演されたラスト・ステージに至るまで、国内外で高い評価を得てきた。『神の子どもたちはみな踊る』も蜷川による演出が予定されていたが、その死により、劇作家・脚本家・演出家の倉持裕に演出がバトンタッチされた。ちなみに、ノーベル賞作家カズオ・イシグロの『わたしを離さないで』を蜷川が演出した際、倉持が脚色を手がけたという縁がある。

撮影:宮川舞子
舞台は、段ボール箱とおぼしき物体が三方に天井高く隙間なく積み重ねられた空間で展開。「蜂蜜パイ」の主人公である作家の淳平(古川雄輝)が執筆しているのが「かえるくん、東京を救う」という構造になっており、キャストはときに複数の役柄を演じ分ける。倉持の演出は、二つの世界を行き来する複雑な構造の戯曲をよく整理し、わかりやすくスピーディに展開。中根聡子の美術も深い印象を残す。

木場勝己 撮影:宮川舞子
そして、何と言っても、「かえるくん」と「語り手」を演じる木場勝己がすばらしい。木場は蜷川演出の『海辺のカフカ』において、知的障害があるものの猫と会話ができる「ナカタさん」に扮して名演を見せており、演出家が亡くなった後の上演でもその魂を伝える上で重要な役割を果たしていた。「かえるくん、東京を救う」では、冴えないサラリーマン片桐(川口覚)の前に、2メートルはあろうかという蛙の「かえるくん」が現れる。「かえるくん」は片桐に、地底で眠っていた「みみずくん」が神戸の地震で目を覚まし、東京に大震災を起こそうとしていることを告げ、それを止めるための自分の戦いに手を貸してほしいと頼む。困惑しながらも片桐は承諾する。「かえるくん」を演じる木場は、蛙のかぶりものと手は装着しているものの、着ぐるみを着用しているというわけではない。その上で、自分は蛙であると告げる、ある種幻想的なセリフに説得力をまずは持たせなければ、今回の作品自体、成立しないところがある。そして、木場が語る「かえるくん」の真摯な言葉に耳を傾けていると、…不思議なことに、次第に、彼が巨大な蛙に見えてくる。「語り手」との二役を担当する木場の身体を通じて、村上春樹の言葉が心の奥底に届けられ、しみ渡ってゆく感触が心地よい。

左:木場勝己 中央:松井玲奈 右:川口覚 撮影:宮川舞子
『海辺のカフカ』を観ての感覚にも通じるが、『神の子どもたちはみな踊る』においても、この世に生まれた人間、その一人一人に与えられた生におけるそれぞれの使命について考えずにはいられない。「ナカタさん」にも「かえるくん」にも使命があり、一見冴えないサラリーマンである片桐にもまた、「みみずくん」との戦いにおいて「かえるくん」を助けるという使命があることがわかる。人の生は、あるときには明らかな、そしてあるときには一見わかりにくい輪によって、つながっている。それぞれの使命もまた然り。壮絶な戦いの果て、「かえるくん」は「みみずくん」との戦いをイーブンに持ち込み、東京の大地震は阻止される。そのとき、「かえるくん」と片桐が果たした役割は、二人以外に知るものはない。そのようにして、この世界は回っている。自分の人生について、いま一度振り返ってみたくなる作品である。
(8月1日14時、よみうり大手町ホールにて観劇)
文=藤本真由(舞台評論家)
<公演情報>
8/21(水)・22(木)【チケット発売中】
舞台「神の子どもたちはみな踊る after the quake」
◼️会場/東海市芸術劇場 大ホール
◼️料金(税込)/全席指定 ¥10,000
◼️開演/8月21日(水)19:00 8月22日(木)13:00
◼️お問合せ/CBCテレビ事業部 TEL.052-241-8118
※未就学児入場不可

日本で30年あまり上演され続けている氷上のミュージカル「ディズニー・オン・アイス」。世代を超え、夢と希望にあふれているからこそ、変わらず愛され続けている作品です。みなさんにも、お気に入りのディズニーキャラクターがいるはず。そのキャラクターたちが、氷の上でパフォーマンスを繰り広げ、華麗なスケーティングで魅了してくれます。
そのディズニー・オン・アイス名古屋公演が、ついに開幕しました。初日には特別にプレショーが行われ、スペシャルサポーターの中川翔子さんと、特別ゲストとしてフィギュアスケーターの小塚崇彦さんが登場。会場が熱気に包まれました。その様子を含め、本作品の魅力をお伝えします!
開幕した8月2日の夜公演、開演15分前にプレショーがスタート。ラプンツェル風の紫色のドレスで登場した中川翔子さんに、大きな歓声と拍手がわきました。続いて、特別ゲストの小塚崇彦さんが、グリーンのベストを着して登場。ラプンツェルの親友であるカメレオンのパスカルをイメージして、グリーンのベストをチョイスしたのだとか。

「これからミラクルなことが起こるんです!」と興奮気味に話した中川さんは、映画「塔の上のラプンツェル」の中から「自由への扉」を歌唱。その生歌に合わせ、リンクでは小塚さんが華麗なスケートを披露してくれました。ディズニー・オン・アイスの始まりにふさわしい、まさにミラクルなスペシャルコラボレーションで、大きな期待が膨らみます。続いて、プーさんとティガーが客席に登場。お客さんと音楽に合わせてジャンプし、会場が一体化。子どもも大人もみんな笑顔に。ミッキー、ミニー、ドナルド、グーフィーもリンクに登場し、大きな歓声が響き渡りました。

そして、いよいよ本編のスタート! 本作品の今年のテーマは“LIVE YOUR DREAMS~あなたの夢は何ですか?~”。プリンセスたちが夢を追い求める姿が描かれています。
第一部は「美女と野獣」、初登場の「リメンバー・ミー」、「塔の上のラプンツェル」。第二部は「シンデレラ」、「アナと雪の女王」、「モアナと伝説の海」の世界へ。ペアスケーティング、グループスケーティングに加え、天井から吊るした布を使って空中パフォーマンスをするエアリアルでは、ラプンツェルとフリン・ライダーが高さ10mの宙を優雅に舞います。
プリンセスたちにはみな夢があり、その夢を叶えるために立ち向かう姿は、勇敢でたくましくもあり、美しい。困難にひるむことなく、本当の自分探しや真実の愛を発見しながら、希望に満ちた人生を信じて前進し続けます。だからこそ、我々は魅了され、何度でも観たくなってしまうのではないでしょうか。
作品の魅力は、華麗な滑りやストーリー性のある構成だけではなく、なんといっても近くまでキャラクターが来てくれること! キャラクターとタッチもでき、大人も子どもも瞬時に夢の世界へひとっ飛び。非現実へといざなってくれます。

また、ディズニーキャラクターになりきって全身コスチュームで来場すると、もれなくオリジナルグッズをもらえる“コスチューム特典公演”や、4人以上でおそろいのコーディネートした来場者には、ミッキーと記念撮影できるチャンスが得られる“おそろコーデ特典公演”もあります。入場口でミッキーがお出迎えしてくれる“グリーティング公演”もあり、ファンにはたまらないサービスがてんこ盛りのディズニー・オン・アイス。この夏、夢探しの旅へ出かけてみませんか?
<公演概要>
8/2FRIDAY〜12MONDAY・HOLIDAY
『ディズニー・オン・アイス』名古屋公演
◼️会場/ドルフィンズアリーナ(愛知県体育館)※昨年までの会場と異なりますのでご注意ください。
◼️公演スケジュール、料金はホームページをご参照ください。http://cte.jp/doi2019
◼️お問合せ/ディズニー・オン・アイス中京テレビ事務局 TEL.052-571-7800(平日10:00〜17:00)
2019年07月01日 <観劇レポート!>ケラ演出・妻夫木聡主演の傑作舞台「キネマと恋人」が待望の再演!!

撮影:御堂義乗
ウディ・アレンの傑作映画『カイロと紫のバラ』の物語をベースに、舞台を昭和36年の日本の架空の離れ小島に置き換えて描くケラリーノ・サンドロヴィッチ作・演出の『キネマと恋人』。好評を博した初演から3年、待望の再演が実現した。初演の際は東京・三軒茶屋のシアタートラムでの公演だったが、再演はより客席数の多い世田谷パブリックシアターへとトランスファー、スタッフ・キャストがほぼ再結集しての上演となった。作品は現在全国公演中だが、その東京公演の模様をレポートしよう。
東京から遠く離れた小さな島にある映画館「梟島キネマ」に、毎日のように同じ映画を観に通うハルコ(緒川たまき)。不況の中、失業している夫は横暴だが、映画を観ているときだけ彼女は現実を忘れられるのだった。そんなある日、彼女が見つめる『月之輪半次郎捕物帖』のスクリーンから、彼女が大好きな俳優高木高助(妻夫木聡)が扮しているキャラクター「間坂寅蔵」(妻夫木聡の二役)が飛び出してくる。共に過ごす時間を楽しむうち、恋に落ちるハルコと「寅蔵」。一方、キャラクターを一人欠いた映画は大混乱、梟島にロケで滞在中だった高助も迷惑を被る。そして、「寅蔵」を探し始めた高助も、ハルコと出会い、恋に落ちる。役者と、彼が演じる架空のキャラクター、“二人”の間で揺れ動くハルコの選ぶ道とは――。
「チーク・トゥ・チーク」や「私の青空」といった戦前の人気メロディがレトロなムードを盛り上げる中、繰り広げられるこの舞台。緒川たまきは、そのたおやかで古風なたたずまいが、夢見る少女の風情を残したヒロインにぴったり。どこか浮世離れした個性をたたえた彼女の好演が、この奇想天外なおとぎ話の成立を支えている。架空の方言を繰り出す様も実にチャーミング。うっとりとした表情、せつない表情、緒川の生き生きとしたさまざまな表情が強い印象を残す。妻夫木聡も、役者と、その役者が演じた架空のキャラクターという二役に扮して魅力を発揮する。とりわけ、スクリーンの時代劇からハルコに惚れて飛び出し、現実感をまったく持たない素直で素朴な言動で周囲を和ませる「寅蔵」役を演じて実に愛らしい。

撮影:御堂義乗
スクリーンから、キャラクターが飛び出す。舞台上の生身の役者の演技と、映像の中のキャラクターの演技とが絡み合って織り成す大混乱は抱腹絶倒もの。映像の中、ストーリーを進めずサボタージュするキャラクター達の姿に熱心に見入り、これを「傑作」と評する人物も現れるあたり、皮肉が利いている。
ハルコが選ぶのは、「寅蔵」か、高助か――。主演俳優と実際に男女の関係をもってしまい、その男にあっけなく捨てられるハルコの妹ミチル(ともさかりえ)を登場させたことで、元となった映画『カイロの紫のバラ』より一層辛口な味わいとなったこの物語。人は、映画や舞台、ドラマといった虚構にいったい何を求め、これを観るのか。役者の演技を愛することは、いったいどのような階層において成立するものなのか――例えば、さきほど、この作品における妻夫木聡の演技について、「寅蔵」役の方により好ましさを表明したけれども、ある役者が演じる複数の役を比較してその役者の魅力を探るという行為自体に、この舞台において劇作家が客席に投げかける“罠”のような問いに引っかかっているのではないかと自問自答させられる。虚構なるものが現実にもたらす救いの陥穽を描いて、ビターな波紋を心に残す作品である。
文=藤本真由(舞台評論家)

撮影:御堂義乗
<公演概要>
7/12FRIDAY〜15MONDAY・HOLIDAY
世田谷パブリックシアター+KERA・MAP#009
舞台『キネマと恋人』
◎台本・演出/ケラリーノ・サンドロヴィッチ
◎出演/妻夫木聡、緒川たまき、ともさかりえ、他
◼️会場/名古屋市芸術創造センター
◼️開演/
7月12日(金)18:30、7月13日(土)・14日(日)13:00、18:00、7月15日(月・祝)13:00
◼️料金(税込)/全席指定¥8,500
◼️お問合せ/中京テレビ事業 TEL.052-588-4477(平日10:00〜17:00)
※未就学児入場不可
◎共催/名古屋市文化振興事業団(名古屋市芸術創造センター)
2019年06月18日 <会見レポート>ネザーランド・ダンス・カンパニーが13年振りとなる待望の来日公演!
世界有数のコンテンポラリー・ダンス・カンパニーであるオランダのネザーランド・ダンス・シアターが、13年ぶりに待望の来日公演を行なう。今年創立60周年を迎える同カンパニーは、1970年代後半に世界的な振付家イリ・キリアンを芸術監督に迎え、キリアンをはじめ優れた振付家たちの作品を次々と踊って躍進を遂げた。メイン・カンパニーのNDTⅠ、若手が所属するNDTⅡの二つのカンパニーから成り、かつては40歳以上のダンサーで構成されるNDTⅢも存在。1990年の初来日以来、キリアン体制のもとで何度も来日を果たしており、現在芸術監督を務めるポール・ライトフットも、かつての来日公演にダンサーとして何度も参加してきた人物だ。日本人振付家・ダンサーを輩出してきたことでも知られ、首藤康之とのコラボレーション等で知られる中村恩恵、Kバレエカンパニーとコラボレーションも行なっている渡辺レイはNDTⅠの出身。日本で初めての劇場専属プロフェッショナル・ダンス・カンパニーであるNoism芸術監督の金森穣、森山未來とのコラボレーション等で知られる大植真太郎はNDTⅡの出身であり、現在は総勢44名中4名の日本人ダンサーが在籍している。

撮影/羽鳥直志
会見が行なわれたのは東京港区のオランダ王国大使公邸。冒頭あいさつに立ったアルト・ヤコビ駐日オランダ王国大使は、かつて中国の北京で大使を務めていた際にNDTの舞台を観劇した経験にふれ、「自分はセンチメンタルな人間ではないけれども、舞台の美しさに涙した。そのNDTの13年ぶりの来日公演が実現したことがうれしい」と思いを語った。
会見には、芸術監督で専任振付家のポール・ライトフット、NDTⅠのダンサーで今回の来日公演で上演される『Shoot the Moon』でメイン・キャストを務める刈谷円香、愛知県芸術劇場シニア・プロデューサーの唐津絵理、そしてゲストとして、NDTⅠ出身の振付家・ダンサーである中村恩恵と小㞍健太が出席した。
今回の来日公演のプロデューサーを務める唐津からは、今回は総勢50名の引越公演となり、装置も大がかりなプロダクションで、選び抜かれた4作品を上演することが発表された。そして映像によってその4作品が紹介された。『Shoot the Moon』は、ポール・ライトフットとアソシエイト・コリオグラファーであるソル・レオンの共同振付で、フィリップ・グラスによるきりきりと心を締め付けるような音楽が印象的な作品だ。『Woke up Blind』はアソシエイト・コリオグラファーであるマルコ・ゲッケの振付。アメリカのシンガーソングライター、ジェフ・バックリィの楽曲を使用しており、腕のムーヴメントに独特なものがある。『The Statement』も同じくアソシエイト・コリオグラファーのクリスタル・パイト振付作。テキストを読み上げる声が流れる中、シャツにパンツという姿の4名のダンサーたちが踊る。そして『Singulière Odyssée』もレオン&ライトフット作品。ダンス作品のためにオリジナルで作曲されたマックス・リヒターの美しい音楽が流れ、衣裳も魅力に富んでいる。

芸術監督のポール・ライトフット(撮影/羽鳥直志)
この後、ポール・ライトフット芸術監督が挨拶。13年前の来日公演には振付家として、その前の来日公演にはダンサーとして参加していた彼は、2011年にNDTの芸術監督に就任しており、今回が芸術監督として最初にして最後の来日公演となる(今シーズンで退任予定)。来日公演について「夢がかないました」と笑顔を浮かべる彼は、「かつて三年に一度くらい、ダンサーとして来日していて、そのとき、日本の観客がNDTを受け入れてくれていること、日本との芸術上の強い結びつきを感じていた」とのこと。「NDTは“進化”“変化”のダンス・カンパニーです。クラシックの伝統とモダンの伝統とを用い、過去に生きるのではなく今を生きる作品を上演してきました。創立60年で約800もの作品を初演してきていて、来日していなかった13年の間でも、さまざまな変化が生じている。その変化をぜひ観ていただきたい」と抱負を語った。
自作『Shoot the Moon』は、「ダンス・シアターというカンパニー名にふさわしい、バレエというより演劇的な作品を創りたい」との意図のもと振り付けた作品であるとか。三つの部屋が常に回転している舞台装置の中で、5人のダンサーが踊る。そして、観客からは見えない場所にカメラがあり、カメラが映している映像も観客に見えるようになっているという趣向が凝らされていて、「25分の上演時間の中で濃密な人間関係を知ることができる」作品とのこと。

©️Rahi Rezvani
アソシエイト・コリオグラファーのゲッケとパイトについては、「世界的にも有名な、重要な存在で、NDTではシーズン一作品ずつ新作を提供してもらっている。『Woke up Blind』と『The Statement』は同じ晩に共に初演されたという経緯があり、二つの完璧に異なる世界が続けて上演されることになる」とのこと。ゲッケについては、「非常にエキセントリックでセンシティブであるけれども、ユーモアと魅力をもった人物で、作品に温かみがある。スピード感と超絶技巧とを両立させ、ダンサーから感情を引き出す手腕がすごい」とその魅力を語った。ゲッケ作品が抽象的なら、続くパイト作品は「メッセージ性の強い作風」。パイトがカナダ人劇作家ジョナサン・ヤングと共に書き上げた短編戯曲が朗読され、4名のダンサーによる会議の場が描かれる作品について、「ダンサー自身は語らないけれども、“身体的叙述”が見られる、もっともユニークなダンス作品の一つ」と分析。パイトはカナダ・バンクーバー在住のため、送られた映像をもとにダンサーが踊り、その映像を再びパイトのもとに送るというプロセスを踏んでの振付となったとか。

©️Rahi Rezvani
締めくくりに上演される『Singulière Odyssée』もレオン&ライトフット作品だが、ライトフットがヨーロッパを旅していたとき、フランス、スイス、ドイツの電車が発着するスイスのバーゼルの駅に降り立ってインスピレーションを得たとのこと。「政治的な提起としてではないけれども、世界における“ムーヴメント”、すなわち、人の行き交い、難民や移動や移住を描きたかった」そう。ちなみにタイトルは“特別な旅”を表すフランス語だが、フランス語で名づけられたのは、NDTの重要メンバーであったフランス人ダンサー、ジェラール・ルメートルの死に捧げるものとして創作されたためとか(1990年代後半にNDTⅢが来日公演を行なった際、筆者は、重ねてきた人生の年輪が自然とにじみ出るようなパフォーマンスに心打たれたことが今でも非常に思い出深いのだが、そのダンサーこそジェラール・ルメートルであった)。

NDT1の日本人ダンサー 刈谷円香(撮影/羽鳥直志)
ここで、『Shoot the Moon』でメイン・キャストを務める刈谷円香が挨拶。NDTⅡで3年過ごした後、NDTⅠに昇格して2年目となる。「来日公演に参加するのが夢でした。作品には、黒のドレスの女性とピンクのドレスの女性、二人の女性が登場し、私は黒のドレスの女性を踊るのですが、私自身は、二人の女性の間には何かしら関係性があるようにとらえて表現しています。5名のダンサーの感情、男女の関係性が強く出ていて、ご覧になった方がそれぞれの思いで理解できる作品だと思います」とその魅力を語った。なお、今回の来日公演には刈谷のほか、高浦幸乃、飯田利奈子と3名の日本人ダンサーが出演予定である。
最後に、かつてNDTに所属し、卒業後も幅広く活躍する中村恩恵と小㞍健太が来日公演に向けてエールを送った。中村は最近NDTの公演を改めて観る機会があった際、「若い人たちがたくさん観に行っていて、帰りのバスで舞台について活発な議論が起きていた。すごく知的好奇心をかきたてるダンス・カンパニーであり続けているのだと思った」とその印象を。「自分の国で踊るのは特別なことですから、踊りたかったですね」と率直な思いを語った小㞍は、「NDTは男性の方が多くキャスティングされる作品が多いけれども、そんな中で、Ⅱで生き抜いて見事Ⅰへと入るのは非常にタフなこと」と後輩ダンサーたちを称賛し、「どの時代も、NDTのダンサーたちは輝いていて、全力で踊ることを全うしている」と、来日公演にますます期待を抱かせる温かな言葉を送っていた。
取材・文=藤本真由(舞台評論家)

©️Rahi Rezvani
<公演情報>
6/28FRIDAY・29SATURDAY【チケット発売中】
ネザーランド・ダンス・シアター
◼️会場/愛知県芸術劇場大ホール
◼️開演/各日14:00
◼️料金(税込)/
S¥12,000 A¥9,000(U25¥4,500) B¥6,000(U25¥3,000) C¥4,000(U25¥2,000)
◼️お問合せ/愛知県芸術劇場 TEL.052-971-5609
※4歳以下入場不可※U25は公演日に25歳以下対象(要証明書)
※託児サービスあり(対象:万1歳以上の未就学児・有料・要予約)
※やむを得ない事情により内容、出演者が変更になる場合があります
※6/28(土)公演のS席は学校団体鑑賞が入るため販売がありません